
取組事例~丸喜産業株式会社②
- プラスチック製品製造業
- #プラスチック製品製造業、生産設備、脱炭素、みんなの脱炭素セミナー、 ロードマップ、SHIFT事業
- #生産設備
2022/11/07
自らを知るための脱炭素診断
事前準備
弊社が支援した丸喜産業様の、環境省のSHIFT事業への申請は、8月上旬に無事採択通知が届きました。そこで、脱炭素診断に向けての準備にとりかかることとなりました。
まずは脱炭素診断を始めるために、クライアントと弊社とでオンラインミーティングを開催します。そこでは事業所の特徴について、何を製造しているのか、どういった工程で、どのような設備が稼働しているのか、そして、それらの設備でどの程度のエネルギーを消費しているのかなど、現地調査の実施計画を作成するために必要となる情報を聞き取りします。この事前のヒアリングより、電力消費のおおよそ7割程度を生産設備が占めていることがわかったため、生産設備を中心に診断する方針となりました。
丸喜産業様においては、入荷した再生プラスチックを粉砕する粉砕機と、押出機が主要なターゲット設備です。一般的には、コンプレッサーや空調機などが診断対象となることが多いのですが、こちらのような製造業の工場ではユーティリティー設備の診断に重点を置いてもあまり効果的ではありません。カーボンニュートラルでは、製品設計の仕方のようなこれまでの当たり前を見直し、将来に備える取り組みが非常に重要となっています。弊社でも生産設備の診断は簡単なものではありませんが、貢献できるようチャレンジしています。
現地調査
調査当日には、事前のオンラインミーティングでの確認事項を共有し、現地の確認を行います。まずは素材側から、工場で使用する素材がどのような設備で加工され、製品として出荷されるか工程を確認していきます。そのなかで、ユーティリティーから圧縮空気、冷水、温水、蒸気がどのように供給されているかを確認します。
そして、エネルギーの消費が大きな設備を特定し、その設備に関して、エネルギーの無駄な利用がないか、効率の悪い設備がないかというようなエネルギー収支を確認することで、削減のポテンシャルを探ります。
次に、それらの装置の仕様と台数を調査し、装置の能力や消費電力などを確認していきます。
削減のポテンシャルを提示する際には、さまざまな技術的な計算を行うわけですが、そこで重要なのが、状態の定量化です。残念ながらどんなに優秀な診断員でも、その設備が何時間稼働しているか、負荷(100%の機器の能力に対して何%の能力で運転しているか)はどの程度かかっているのか、そのうち生産に寄与している時間はどの程度か、逆に無駄な時間はどの程度かといった状態を、見ただけで把握することはできません。それらを確認するためには、やはりデータの計測が重要なポイントとなります。
今回の丸喜産業様の診断では、粉砕機と押出機を中心に合計約40カ所の電流値の計測を行いました。ただし、この計測器の設置はやはり大変な作業です。計測箇所を初見で決めるには熟練を必要とし、炎天下などの過酷な環境の場合は設置作業の体力もまた必要です。そして計測器を設置してから、データ収集を2週間ほど行います。
診断結果の分析
現地での確認結果から、装置の仕様と計測データを得ることで実際の運転条件などがある程度把握できる状態になります。ただし、生産量などの情報は、クライアントに別途準備をしていただきます。
そしてそれらの情報を基に、分析を開始します。パレート図を使った対象設備の優先順位付けやエネルギーフロー図の作成、エネルギー原単位分析、データを検証しながらの稼働状況確認など、さまざまな分析を行いながら、重要な課題を抽出していきます。
対策案の立案
診断の分析の結果、課題についてさまざまな対策案が抽出されます。
一般的な対策であるLED化や変圧器の高効率化、太陽光の自家消費、低炭素電力への切り替えなどは、当然のポテンシャルとして抽出します。
また、弊社の診断の特徴である生産設備の分析により、エネルギー原単位分析を行いました。その結果、押出機自体の稼働率と負荷率が小さく、エネルギー利用上問題があることがわかりました。
ただし、この問題は従来の設備利用を前提として改善を試みても、大きな改善にはつながりません。
この本質的な課題である、生産設備の粉砕機と押出機のシステム構成に関して、長期的にカーボンニュートラルに適したシステム構成への変更が必要だという結論に至りました。
一般的なLED化などは、弊社でも多くの実績があるため費用対効果など明確にして報告書にまとめます。しかし、生産設備、特に今回の押出機のようにオーダーメイド要素の大きい設備に関しては、費用対効果まで明確にすることはできません。とはいえ、重要なテーマであるため、必ず報告を行います。生産設備については、現状の課題を明確にし、今後の進め方については長期的なプロジェクトを発足するというご提案といたしました。
計画案の立案
診断結果の報告まで終わった段階で、これから2030年と2050年のSDGsの目標に向けた計画を立案します。費用対効果の良いLED化などがすぐにできる対策となりますが、太陽光などは屋根強度の問題もあるため、簡単に実現できるわけではありません。将来的に行う建屋改修などと併せた長期的な取り組みとなります。
また生産設備については、やはり多額の投資が必要となります。この点に関しては、丸喜産業の小園社長より、毎年計画的に実施していくという方針が示されました。一つひとつ計画に落とし込んでいった結果、削減ボリュームとして2030年にある程度の削減が可能となる計画を策定できました。
この診断結果の報告時には、診断結果と策定した計画だけではなく、その後の進め方として、国際認証制度であるSBTの取得や、設備投資の資金調達を支援する補助事業の活用、さらに、今回の計測結果よりCO2の管理が必要ということもわかったため、クラウド式の電力の見える化システムの導入について、選択肢をご案内しています。
CATEGORYカテゴリー
-
業種でさがす
-
設備でさがす
-
お悩みでさがす
-
導入事例でさがす



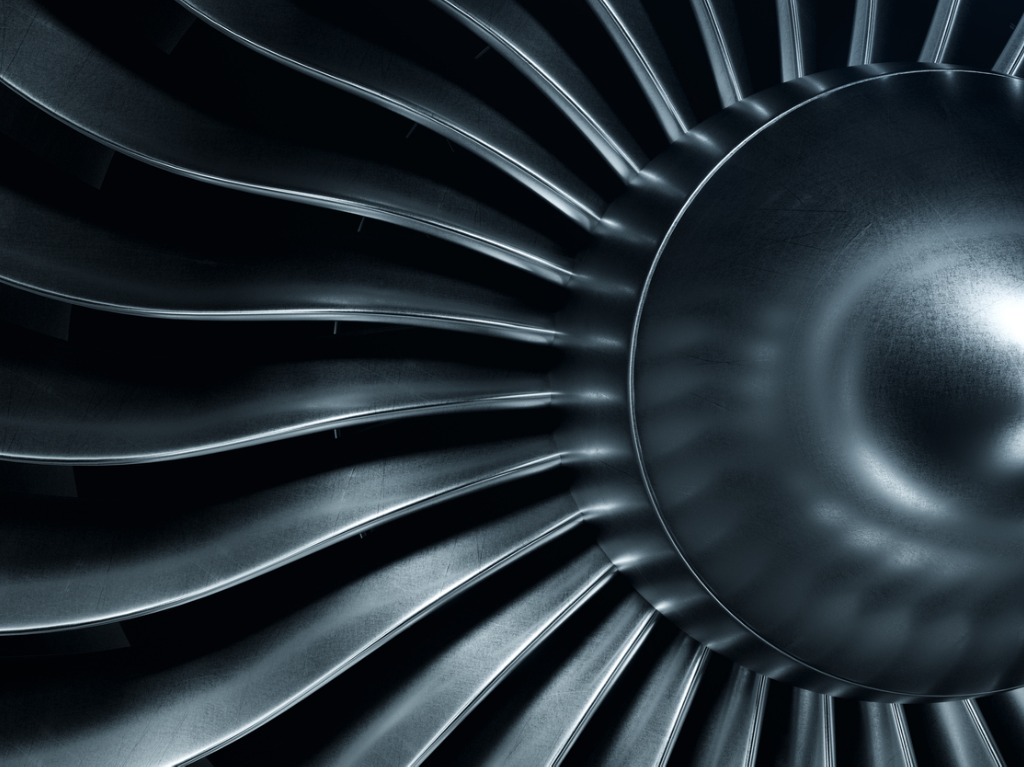




 いますぐ電話
いますぐ電話 お問い合わせ
お問い合わせ
